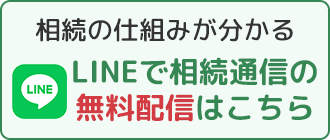相続の相談は誰にべきなの?
相続手続きに関わる専門家 相続が発生するといろいろな手続きが必要になります。手続きは、相続人本人が自ら行うことができるのですが、難しい法律用語が多い上、必要書類も多くなかなか煩雑なものです。 そんな時に頼りになるのが専門家です。でも、相続の専門家って誰なのでしょう??各々の手続きには、法律で決められたその専門家にしかできない業務もあります。 今回はその手続きに関わってくる専門家とそれぞれの仕事をご紹介します。 弁護士 ・・・法律の専門家 遺産分割に争いが生じている場合などに、相続人の代理交渉や紛争を解決するための直接的な法律行為のアドバイスを行います。このような業務は弁護士のみが行うことができ…