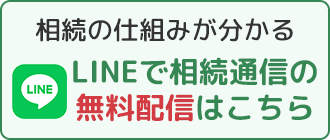相続登記の義務化(ニュースレター令和6年3・4月号 )
2024年4月より「相続登記の義務化」が施行され、不動産を相続した場合、取得から3年以内に登記を行うことが法律で義務化されました。これに違反すると、10万円以下の過料が課される可能性があります。この制度は、不動産の所有者を明確にし、相続手続きを円滑にするための重要な変更です。 今後の相続対策において、早めの登記が不可欠です。 相続により不動産を取得され、まだ登記がお済でない方はお早目にお手続きください。 ①改正の内容 相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが法律上の義務になります。 〇制度の開始・・・2024年4月1日より 〇義務の対象範…