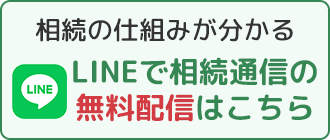ニュースレター令和5年3・4月号 相続時精算課税制度の基礎控除の新設
令和5年度税制改正において、贈与の分野に大きな改正がありました。 今回は相続時精算課税制度の「年間110万円の基礎控除」の新設について説明します。 相続時精算課税制度とは 原則60歳以上の父母、祖父母から18歳以上の直系卑属である子や孫に生前贈与をする際において選択できる贈与税の制度で、以下の特徴があります。 ① 合計2,500万円までは贈与税は非課税。贈与額が2,500万円超えた場合は超えた額に対して一律20%の贈与税がかかる。 ② 贈与を受けた金額は、全て相続財産に足し戻して計算するため相続税がかかる。その際、すでに納付した贈与税は控除される。 ③ 相続時精算課税制度を選択すると暦年課税制…