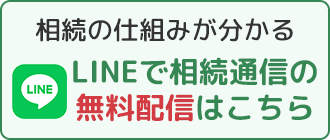数年前に亡くなった親名義の土地がある場合の相続税申告
ご相談いただいた時点での状況 お母様が亡くなられたということで、相続税申告の可能性があるかも知れないということで、ご相談をいただきました。 相続人となる方はご相談者様のみという状況でしたが、相続財産として預貯金の他に数年前に亡くなったお父様の名義となっている土地があり、この土地が相続財産として含まれるのかが心配で専門家への相談を希望されておりました。 ご相談内容に対しての当事務所からの提案と結果 預貯金に関しては、お母様の名義となっている財産でしたが、お父様名義の土地については、そのままお父様名義のままとし、お母様の相続税申告の際には、預貯金のみを相続財産として、申告をする事を提案いた…